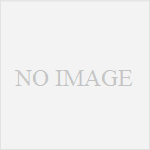キョクトウトカゲモドキ

キョクトウトカゲモドキたちを知っていますか?
ベトナムや中国などに生息するトカゲモドキの仲間です。
彼らは属名のgoniurosaurusから通称「ゴニ」と呼ばれています。
あのヒョウモントカゲモドキの近縁種ですが、性質、飼育方法、ありとあらゆる面でまったく異なっています。
性格はまさに
「陰気」
飼い主を見れば寄ってくるヒョウモントカゲモドキとはわけが違います。
飼育していてもなかなか姿を現さないので、まれに観察できれば超ラッキーってな感じです。
しかし、そんな陰気な彼らですが見た目は超絶かっこいい。
全体的に細身の体型や黒や黄色のバンド模様。赤色の目。厳つい顔つき。
世の中に悪魔がいるというのなら彼らのような姿をしているかもしれません。
そんな風に思わせる凄みを持っています。
今回はそんな彼らについて迫っていきます。
スポンサーリンク
この記事の目次
➀キョクトウトカゲモドキの魅力と現状
彼らの魅力は何といっても、そのかっこよさ。
繰り返しになりますが、黒や黄色の色彩に、紅い目が非常にかっこいいです。
悪魔や龍のようだと良く形容されますが、私もその通りだと思います。
次に彼らの持つコレクション性もまた魅力の一つかなと感じます。
キョクトウトカゲモドキの仲間は何種類か流通していますが、どれもよく見ると姿が異なりバラエティーに富んでいます。
流通しにくい種類もいますが、手元に何種か集めて見比べたいですね。
実は、彼らの仲間は日本にもいます。
トカゲモドキなんて日本にいないでしょ!って思うかもしれません。
が、それは誤った認識です。
日本には沖縄を中心に2種(亜種含めれば6種類)のキョクトウトカゲモドキの仲間が生息しています。
➀オビトカゲモドキ
➁クロイワトカゲモドキ
-
クメトカゲモドキ
-
クロイワトカゲモドキ
-
ケラマトカゲモドキ
-
マダラトカゲモドキ
- イヘヤトカゲモドキ
2003年までオビトカゲモドキだけは飼育が可能でしたが、個体数の減少が問題視され現在ではこれら全種類が天然記念物に指定されているため飼育ができません。
そういうわけで、現時点で飼育が可能なキョクトウトカゲモドキである、ベトナムや中国の種類のものは非常に重宝されるのです。
ただし!!!
海外のキョクトウトカゲモドキ達も生息環境の悪化や、気候変動、ペット目的による捕獲などにより個体数が著しく減少しているようです。
今も野生採取の個体がよく流通していますが、飼育する場合は必ず繁殖させ、市場に流通させてほしいです。
私が個人的にキョクトウトカゲモドキが好きという気持ちもありますが、繁殖させてほしいです。
繁殖させる気がないなら飼育しないでほしいです。
意味不明な発言に聞こえるかもしれませんが、生半可な気持ちで飼育していい生き物ではないと私は思っています。
その点、ハイナントカゲモドキは多種と比べると物怖じしにくく、繁殖も容易な方なのでおすすめです。
この種が飼育・繁殖できないなら、他のキョクトウトカゲモドキの飼育は諦めるべきです。
➁主なキョクトウトカゲモドキ8種紹介
1.ハイナントカゲモドキ

学名:Goniurosaurus hainanensis
英名:Hainan Far East Gecko
分布:中国(海南島)
全長:14~16㎝程度、最大17㎝
価格:6000~10000円前後
解説
かつては幻の種でした。
この仲間では最も飼育繁殖がしやすいと言われています。
海抜81~765mまでの高度で発見される調査結果もあり、低地型と高地型の個体群がいるようです。
生息域によって、色彩や模様が微妙に異なります。
形態の大きな特徴としては、明るい灰色と薄茶色をベースに黒色に縁どられた4本の黄色いバンド模様が挙げられます。。
バンド模様は、年齢を重ねるごとに薄れていく傾向にあります。
2.ゴマバラトカゲモドキ
別名:ルイー、チュウゴクトカゲモドキ、ピンシャントカゲモドキ
学名:Goniurosaurus luii
英名:Chinese Leopard Gecko, Chinese Cave Gecko
分布:中国とベトナムの国境周辺
全長:20cm程度
価格:10000~20000円程度
解説
1999年に新種記載されました。
ハイナントカゲモドキによく似ています。
ただ、体はこちらの方が大きいですし、四肢も長く、バンドも4~5本、バンドの色は美しいオレンジ色ということで見分けることができます。
ゴマバラトカゲモドキという名で入荷されるものの、入荷便によって個体差がかなりあります。
もしかしたら、現在本種として流通する種が分けられる可能性もあります。
異なる入荷便の個体での繁殖は避けたほうが無難です。
飼育難易度はハイナントカゲモドキと比べると難しいです。
自身がない方は、ワイルド個体(WC)は避け飼育下繁殖個体(CB)を購入するようにしましょう。
3.バワリントカゲモドキ
学名:Goniurosaurus bawanglingensis
英名:Bawangling Far East Gecko
分布:中国海南島の覇王嶺国家級自然保護区
全長:最大16㎝程度
価格:30000~50000円程度
解説
2002年に新種記載されました。
体型はハイナントカゲモドキによく似ています。
黄色をベースに無数の暗い斑紋が入る美しい種です。
幼体時は他の種同様にバンド模様がありますが、成長とともに消えていきます。
飼育・繁殖自体は容易な部類です。
4.カットバトカゲモドキ
学名:Goniurosaurus catbaensis
英名:Catba far east gecko
分布:ベトナム カットバ島
全長:20cm程度
価格:70000~80000円程度
解説
比較的物怖じしない性格ゆえに、ピンセットでエサを食べる個体もいるとか。
そういうわけで飼育・繁殖は容易な部類。
成長するにつれて、オレンジ模様と粒状突起が発達し、非常に美しいです。
5.ベトナムトカゲモドキ
別名:アシナガトカゲモドキ、アラネウス
学名:Goniurosaurus araneus
英名:Vietnamese Leopard Gecko
分布:ベトナム(カオバン省)
全長:最大20㎝
価格:30000~60000円程度
解説
キョクトウトカゲモドキの仲間で最大種と言われています。
生息地は主に岩だらけのカルスト。
そういった環境では彼らの長い足が大きな武器となるのでしょう。
模様がバンド模様のタイプと、ヒョウ柄のタイプの2つが入荷します。
ベトナムには他にもトカゲモドキが生息していることから、アシナガトカゲモドキ、もしくはアラネウスと呼ぶ方が一般的です。
6.インド―トカゲモドキ
別名:イエントトカゲモドキ
学名:Goniurosaurus yingdeensis
英名:Yingde leopard gecko
分布:中国(広東省英徳市)
全長:17㎝程度
価格:60000~80000円程度
解説
2010年に新種記載されました。生息地が非常に限定的で流通数は非常に少ない。
黄色みのオレンジに複雑な模様を持ち非常に美しいです。
インド―トカゲモドキとはインドのことではなく、広東省の英徳市(インド―)のこと。
スポンサーリンク
➂基本的な飼育環境の作り方
どの種も似たような飼育環境で飼育することが可能です。
ポイントをしっかり守って飼育しましょう。
- 飼育ケージ
- 保温器具
- 床材
- シェルター
- 水容器
- エサ
- カルシウム剤
以下で一つ一つ説明していきます。
・飼育ケージ
-1匹での飼育の場合-
小型種➡大きめのプラケース
大型種➡特大サイズプラケース
で十分飼育が可能です。
-ペアないしトリオ(♂1♀2)で飼育する場合-
小型種➡特大サイズプラケース
大型種➡底面積60×30㎝のケージ
を用意すると完璧です。
ケージは必ず通気性が良く、また脱走できないような蓋ができるものを使用しましょう。
・保温器具
キョクトウトカゲモドキの仲間はどれも風通りの良い、多湿かつ冷涼とした環境に生息しています。
最適な温度:24~26℃程度、上限は28℃
暑さが厳しい日本の夏はエアコン管理が必須となります。
寒くなる秋から春にかけてはパネルヒーターをケージ面積の1/3~1/2に敷いて保温してあげましょう。
・床材
湿度を保てる素材を床材にします。
ヤシガラ土、腐葉土、黒土などをブレンドして使用するのがわりと一般的です。
床材は厚めに敷いて、表面はやや乾燥、その表面下やシェルターの下は湿っているという環境が理想的です。
糞を見かけたら、カビが生えてしまうので早急に周辺の床材ごと除去しましょう。
・シェルター
臆病な性格をしているのでシェルターは必須です。
コルクバーグのシェルターと素焼きのウェットシェルターの両方を設置し、選ばせると完璧です。
シェルターは、最低でも飼育して居る個体数以上の数を設置してあげましょう。
💡シェルター設置の注意点・工夫点💡
重いシェルターを床材の上にそのまま設置すると、穴を掘ってシェルターに踏みつぶされそのまま死んでしまうケースがあります。
シェルターを置いてから床材を敷いたり、軽めの素材のシェルターを置くなど対策を取りましょう。
また、キョクトウトカゲモドキの仲間(特に足が長いタイプ)は割と立体活動も行います。
シェルターも立体的なものを使用すると、より飼育が楽しめそうですね。
・水容器
簡単にひっくり返らず、かつあまり重くない容器に水を入れて設置しましょう。
飲み水になるほか、ある程度の湿度を保つ効果もあります。
ただし、水容器を設置していても数日に1回は霧吹きをしましょう。
・エサ
昆虫を与えます。
個人的には動きがあるエサの方が好むように感じますのでコオロギやレッドローチを与えるといいでしょう。
コオロギは食べやすいように後ろ足を取り除いて与えてあげてください。
・カルシウム剤
カルシウムを与えないとクル病などの病気に罹患するリスクが高まります。
クル病は骨の形成がうまくされない病気であり、なかなか治りませんし最悪の場合死に至る恐ろしい病です。
カルシウム剤をエサに毎回必ず塗してから与えるようにしてください。
カルシウム剤には【カルシウム】だけのものと【カルシウム+ビタミンD3】の2種類があります。
※ビタミンD3はカルシウムの吸収を促す効果があります。
普段は【カルシウム】だけのものをエサに塗して与え、たまに【カルシウム+ビタミン】のものを塗して与えてください。
※ビタミンの摂りすぎもクル病と似た症状が出る恐れがあるので注意が必要です。
➃飼育のポイント
彼らの飼育のポイントを3つまとめました。
一つ一つチェックしてあげてください。
1.通気性の良い、多湿、冷涼な環境
➡ケージは通気性のいいものか、またケージの設置場所は風通りがいいか確認しましょう。
霧吹きやブレンドした床材、ウェットシェルターで多湿な環境を作りつつ、エアコンやヒーターで温度調節しましょう。
2.そもそもショップでエサを食べているか
➡繰り返しになりますが、ショップでエサを食べている個体を選ぶというのは購入に踏み切る前提条件です。
よほど自信がない限り、ショップで餌付いていない個体に手を出すのは諦めましょう。
また、餌付いている場合、どの種類の、どの大きさのエサを食べていたか聞いておくと完璧です。
3.ハンドリングはしない
➡彼らは、ハンドリングをされて喜ぶ生き物ではありません。
むしろ大変なストレスとなります。
尾の自切をしてしまうケースもあるので、世話の時以外放置が基本です。
スポンサーリンク
➄基本的な繁殖方法
基本的な繁殖方法はどの種も同じようです。
繁殖は大きな負荷がかかるので焦らずじっくり育て上げた雄雌を使用しましょう!
まず、別で飼育をしていた方が同居させた際にうまく交尾が進むので、多頭飼いしている場合にはケージを別々にします。
冬に近づくにつれて少しずつ給仕の回数を減らし、やがて給仕回数を0にしたら15~20℃程度の低温にしクーリングを1~2カ月程度行います。
この時、水だけは与えるようにします。
クーリング期間終了後、温度を上げ、雌雄を2~3週間同じケージで同居させます。
交尾が確認できたら速やかに雌雄を別にしてください。
交尾後数週間でメスの腹部に卵が確認できるはずです。
彼らは1シーズンに2~6クラッチするようです。
卵は26℃程度で保温すると55~80日程度で孵化します。
産卵した後のメスは非常に疲れ弱っているのでカルシウムをふんだんに塗した高栄養価のエサをたくさん与え体調をととのえてあげてください。
この際の立ち上げがうまくいかないと、そのままメスが死んでしまうこともあります。
➅まだまだ見つかる新種たち
キョクトウトカゲモドキの仲間は、未だに続々と新種が見つかっているグループです。
最近ですと、2013年にリボトカゲモドキ(Goniurosaurus liboensis)、そして去年2018年にはGoniurosaurus zhouiというトカゲモドキが海南島で発見されました。
他のキョクトウトカゲモドキと誤って新種が入荷されているケースもある(といわれている)ようなので、実は自分が買った個体が新種!ってこともあるかもしれません。
夢が広がりますね。
今はまだ見つからぬ、新種たちに思いを馳せながら飼育と繁殖頑張りましょう!
この記事を読んだ人はこの記事も読んでいます